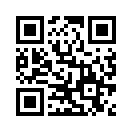2015年09月30日
女性の尿漏れとコンチネンス外来・ウロギネ外来
尿漏れは身近で切実な問題です。
特に女性に尿漏れが多いのには、理由があります。
男性の尿道は約20cmと長く、構造もカーブがあり、安定しています。
一方、女性の尿道は3~4cmと短く、構造も直線的で、男性にくらべると骨盤底筋が薄く、不安定です。
骨盤底筋とは、骨盤底を構成する4つの筋(深会陰横筋、尿道括約筋、肛門挙筋、尾骨筋)の総称です。
恥骨と尾骨の間にあり、尿道・膣と肛門を「8」の字状に取り囲む形をしています。
内臓を支え、尿道や膣、肛門を締める役割があります。
骨盤底筋が弱くなると、瞬間的な腹圧に反応できず、尿漏れを起こします。
骨盤底筋が弱くなる原因には
●加齢
●女性ホルモンの低下
●妊娠・出産
●肥満
●悪い姿勢
などがあげられます。
----------
尿漏れは主に「腹圧性」と「切迫性」に分けられます。
●腹圧性尿失禁:くしゃみや咳、大笑い、重い荷物を持ちあげるなど、瞬間的にお腹に力がかかったときに起こる。
●切迫性尿失禁:冷たい水や寒さなどで膀胱が収縮し、尿意をもよおし、起こる。少ない尿量でも尿意を感じてしまうので、頻尿になりやすい。
さらに、腹圧性と切迫性の混合タイプも存在します。
腹圧性尿失禁の場合、軽度であれば骨盤底筋を鍛えることで、尿もれはかなり改善されます。
一方、切迫性尿失禁の場合は、膀胱の収縮を抑制する薬の投与が選択される傾向にあります。
尿漏れがある場合、自分の症状をチェックしてみましょう。
ケアによって8割の方は症状が改善するそうです。
重症化する前に早めのケアを心がけましょう。
人に相談しづらい悩みですが、今はインターネットから情報収集も可能です。
医療機関は以下のキーワードと居住地域で検索してみてください。
●尿失禁外来
●婦人科外来
●婦人泌尿器科
●泌尿器科
●産婦人科
●女性外来
●婦人泌尿器科
●婦人科外来
●女性専用クリニック
●レディースクリニック
●コンチネンス外来
●ウロギネ外来
コンチネンス(continence)は、排尿制御のこと。
ウロギネとは、ウロ(Urology:泌尿器科)とギネ(Gynecology:婦人科)の合成語だそうです。
2つとも聞きなれない言葉ですが、私的には「尿失禁外来」に受診するよりも抵抗がない感じがします。
病院へ行く前に、無料で電話相談もできます。
よくある相談内容も掲載されていますので、チェックしてみてはいかがでしょうか?
日本コンチネンス協会 排泄の困りごと110番 相談窓口
TEL:050-3786-1145
毎週日曜日、木曜日 10:00~16:00
尿漏れはすべての女性の問題です。
1人で悩まず、まずは相談からはじめてみませんか?
(-人-)~☆
特に女性に尿漏れが多いのには、理由があります。
男性の尿道は約20cmと長く、構造もカーブがあり、安定しています。
一方、女性の尿道は3~4cmと短く、構造も直線的で、男性にくらべると骨盤底筋が薄く、不安定です。
骨盤底筋とは、骨盤底を構成する4つの筋(深会陰横筋、尿道括約筋、肛門挙筋、尾骨筋)の総称です。
恥骨と尾骨の間にあり、尿道・膣と肛門を「8」の字状に取り囲む形をしています。
内臓を支え、尿道や膣、肛門を締める役割があります。
骨盤底筋が弱くなると、瞬間的な腹圧に反応できず、尿漏れを起こします。
骨盤底筋が弱くなる原因には
●加齢
●女性ホルモンの低下
●妊娠・出産
●肥満
●悪い姿勢
などがあげられます。
----------
尿漏れは主に「腹圧性」と「切迫性」に分けられます。
●腹圧性尿失禁:くしゃみや咳、大笑い、重い荷物を持ちあげるなど、瞬間的にお腹に力がかかったときに起こる。
●切迫性尿失禁:冷たい水や寒さなどで膀胱が収縮し、尿意をもよおし、起こる。少ない尿量でも尿意を感じてしまうので、頻尿になりやすい。
さらに、腹圧性と切迫性の混合タイプも存在します。
腹圧性尿失禁の場合、軽度であれば骨盤底筋を鍛えることで、尿もれはかなり改善されます。
一方、切迫性尿失禁の場合は、膀胱の収縮を抑制する薬の投与が選択される傾向にあります。
尿漏れがある場合、自分の症状をチェックしてみましょう。
ケアによって8割の方は症状が改善するそうです。
重症化する前に早めのケアを心がけましょう。
人に相談しづらい悩みですが、今はインターネットから情報収集も可能です。
医療機関は以下のキーワードと居住地域で検索してみてください。
●尿失禁外来
●婦人科外来
●婦人泌尿器科
●泌尿器科
●産婦人科
●女性外来
●婦人泌尿器科
●婦人科外来
●女性専用クリニック
●レディースクリニック
●コンチネンス外来
●ウロギネ外来
コンチネンス(continence)は、排尿制御のこと。
ウロギネとは、ウロ(Urology:泌尿器科)とギネ(Gynecology:婦人科)の合成語だそうです。
2つとも聞きなれない言葉ですが、私的には「尿失禁外来」に受診するよりも抵抗がない感じがします。
病院へ行く前に、無料で電話相談もできます。
よくある相談内容も掲載されていますので、チェックしてみてはいかがでしょうか?
日本コンチネンス協会 排泄の困りごと110番 相談窓口
TEL:050-3786-1145
毎週日曜日、木曜日 10:00~16:00
尿漏れはすべての女性の問題です。
1人で悩まず、まずは相談からはじめてみませんか?
(-人-)~☆
2015年09月29日
【お客様の声】手術の後、鈍くなっていた足の感覚がつながった気がします。(50代女性)
■ 手術の後、鈍くなった足の感覚がつながった気がします。(50代女性)
かなり前に腰椎5番と仙骨の間の椎間板ヘルニア手術を受けました。
手術は無事成功したのですが、左脚の感覚は鈍くなりました。
時々、太腿裏の筋肉がつります。
一度つりはじめると、かなり痛く、長引きます。
施術は主に、腰、仙骨の硬くなった部分、膝裏まわりでした。
多少の痛みが伴いましたが、我慢できるものでした。
仙骨の部分に施術を受けた時、じわじわと温かくなるのを感じました。
いつも、つった感じがするのは左太腿裏の筋肉の太い所だったのですが、施術を受けて違和感を感じたのは別の部分でした。
一通り施術を受けた後、「神経の働きを意識してみましょう」といわれ、腰から足まで、順番にイメージしてみました。
頭では理解していましたが、手術の後、鈍くなっていた足の感覚がつながった気がします。
不思議です。
次回の施術まで、身体の変化を観察してみようと思いました。
足がつらなくなるのではないかと期待しています。
ありがとうございました。
かなり前に腰椎5番と仙骨の間の椎間板ヘルニア手術を受けました。
手術は無事成功したのですが、左脚の感覚は鈍くなりました。
時々、太腿裏の筋肉がつります。
一度つりはじめると、かなり痛く、長引きます。
施術は主に、腰、仙骨の硬くなった部分、膝裏まわりでした。
多少の痛みが伴いましたが、我慢できるものでした。
仙骨の部分に施術を受けた時、じわじわと温かくなるのを感じました。
いつも、つった感じがするのは左太腿裏の筋肉の太い所だったのですが、施術を受けて違和感を感じたのは別の部分でした。
一通り施術を受けた後、「神経の働きを意識してみましょう」といわれ、腰から足まで、順番にイメージしてみました。
頭では理解していましたが、手術の後、鈍くなっていた足の感覚がつながった気がします。
不思議です。
次回の施術まで、身体の変化を観察してみようと思いました。
足がつらなくなるのではないかと期待しています。
ありがとうございました。
2015年09月28日
フェルデンクライスメソッド
フェルデンクライス・プラクティショナーの方とご縁があり、月1回プライベートレッスンを受けています。
フェルデンクライスメソッドは、ソマティックエディケーション(身体教育)。
体の動きをとおして私たちの能力を引き出します。
創始者はモシェ・フェルデンクライス(Moshe Feldenkrais)。
フェルデンクライスは、ロシア生まれの物理学博士。
柔道のエキスパートであり、機械工学の技術者、かつ教育者でもありました。
多彩な方だったんですね。
自らの膝の大けがで苦しんだ後、心理学、神経生理学、その他の身体関連の分野について深く学び、理論を統合し、フェルデンクライスメソッドのシステムを構築しました。
レッスンには、ニーズに合わせた2つの形式があります。
1.グループレッスン:「動きを通しての気づき」(ATM : Awareness through Movement)
2.マンツーマンレッスン:「機能の統合」(FI : Functional Integration)
----------
と説明されると、
「何だか難しそう!」
と思われるかもしれませんが、レッスンは大変楽しいので、ご安心を。
プラクティショナーの誘導で、身体を部分ごとに動かしたり、言葉で表現したり、歩いたり、足を挙げたり…etc。
お子さんでも大丈夫です。
プラクティショナーのシルヴィーさんによれば
「いろいろな動きを入力すれば、脳はその中から最適なものを自ら選び取ります。」
とのこと。
私は骨盤周辺の動きが気になっていたのですが、観ていただいたら、足の使い方に課題が見つかりました。
重心の位置や土踏まずの意識など、左右の違いにもビックリです。
自分の視点には無い、新しい気づきをいただきました。
ありがとうございます。
(-人-)~☆

----------
フェルデンクライスメソッドは、以下の分野に活用されています。
●健康づくりと老化の予防
●幼児・児童など、学習能力や潜在能力の開発
●ダンス・演劇・音楽などの表現力・創造力開発向上
●スポーツ・武道などの上達、動作の安全性・効率性の向上
●けがや障害のある人の機能訓練
【参考】
●日本フェルデンクライス協会
●フェルデンクライス・ジャパン
プラクティショナーもこちらから検索ができます。
フェルデンクライスメソッドは、ソマティックエディケーション(身体教育)。
体の動きをとおして私たちの能力を引き出します。
創始者はモシェ・フェルデンクライス(Moshe Feldenkrais)。
フェルデンクライスは、ロシア生まれの物理学博士。
柔道のエキスパートであり、機械工学の技術者、かつ教育者でもありました。
多彩な方だったんですね。
自らの膝の大けがで苦しんだ後、心理学、神経生理学、その他の身体関連の分野について深く学び、理論を統合し、フェルデンクライスメソッドのシステムを構築しました。
レッスンには、ニーズに合わせた2つの形式があります。
1.グループレッスン:「動きを通しての気づき」(ATM : Awareness through Movement)
2.マンツーマンレッスン:「機能の統合」(FI : Functional Integration)
----------
と説明されると、
「何だか難しそう!」
と思われるかもしれませんが、レッスンは大変楽しいので、ご安心を。
プラクティショナーの誘導で、身体を部分ごとに動かしたり、言葉で表現したり、歩いたり、足を挙げたり…etc。
お子さんでも大丈夫です。
プラクティショナーのシルヴィーさんによれば
「いろいろな動きを入力すれば、脳はその中から最適なものを自ら選び取ります。」
とのこと。
私は骨盤周辺の動きが気になっていたのですが、観ていただいたら、足の使い方に課題が見つかりました。
重心の位置や土踏まずの意識など、左右の違いにもビックリです。
自分の視点には無い、新しい気づきをいただきました。
ありがとうございます。
(-人-)~☆
----------
フェルデンクライスメソッドは、以下の分野に活用されています。
●健康づくりと老化の予防
●幼児・児童など、学習能力や潜在能力の開発
●ダンス・演劇・音楽などの表現力・創造力開発向上
●スポーツ・武道などの上達、動作の安全性・効率性の向上
●けがや障害のある人の機能訓練
【参考】
●日本フェルデンクライス協会
●フェルデンクライス・ジャパン
プラクティショナーもこちらから検索ができます。
2015年09月27日
運動量計を使っております。MISFIT FLASH(ミスフィット フラッシュ)
8月末から運動量計を使っております。
MISFIT FLASH(ミスフィット フラッシュ)。

以前、タニタのカロリズムを使っていたのですが、不携帯なことが多く、電池も切れたことでお蔵入りに。
こちらはウェアラブルタイプなので、腕時計の感覚です。
とはいえ、普段腕時計もしなくなった私。
汗もかきやすいし、仕事上、手を使うので、結構ジャマに感じます。
で、足に巻いています。

靴下の上からが気にならず、私的には良い感じです。
計測できるものは、
●歩数
●距離
●消費カロリー
●睡眠サイクル
30m防水もついているので、通常の生活には問題ないでしょう。
充電が不要で、最大約4ヶ月連続で使えるのも魅力です。
が、ヨガや太極拳を1.5時間やったのに、消費カロリーはほぼ変化なし。
(@_@)?!
取説をみると、運動を認識するセンサーが「3軸 加速度計」となっていました。
なるほど。
加速度がない運動は認識されないのですね。
ちょっと残念ですが、仕方がありません。
シビアに運動量を計測したい場合は、別の機種を選択されるとよいでしょう。
日常生活の計測でしたら、ほぼ問題ないと思います。
アプリの「Link」を使うと、iPhoneの自撮りボタン(リモートシャッター)として利用できます。
これは、ヨガやエクササイズなど、ブログの写真を撮るのに利用できそうですね。
今後の活用法を検討したいと思います。
(-人-)~☆
MISFIT FLASH(ミスフィット フラッシュ)。
以前、タニタのカロリズムを使っていたのですが、不携帯なことが多く、電池も切れたことでお蔵入りに。
こちらはウェアラブルタイプなので、腕時計の感覚です。
とはいえ、普段腕時計もしなくなった私。
汗もかきやすいし、仕事上、手を使うので、結構ジャマに感じます。
で、足に巻いています。
靴下の上からが気にならず、私的には良い感じです。
計測できるものは、
●歩数
●距離
●消費カロリー
●睡眠サイクル
30m防水もついているので、通常の生活には問題ないでしょう。
充電が不要で、最大約4ヶ月連続で使えるのも魅力です。
が、ヨガや太極拳を1.5時間やったのに、消費カロリーはほぼ変化なし。
(@_@)?!
取説をみると、運動を認識するセンサーが「3軸 加速度計」となっていました。
なるほど。
加速度がない運動は認識されないのですね。
ちょっと残念ですが、仕方がありません。
シビアに運動量を計測したい場合は、別の機種を選択されるとよいでしょう。
日常生活の計測でしたら、ほぼ問題ないと思います。
アプリの「Link」を使うと、iPhoneの自撮りボタン(リモートシャッター)として利用できます。
これは、ヨガやエクササイズなど、ブログの写真を撮るのに利用できそうですね。
今後の活用法を検討したいと思います。
(-人-)~☆
2015年09月26日
咳と麦門冬湯(ばくもんどうとう)
久々に風邪をひいたようです。
熱や鼻水はなかったのですが、喉がつらい。
痰がからんで咳がひどく、喉を傷めました。
身体はつらくないので、ヨガへ。
エアコンの風で、咳を連発。
すると、森先生から
「気管支を傷めるから、麦門冬湯(ばくもんどうとう)を飲みなさい!!」
とのアドバイスをいただきました。
帰り道、まだドラッグストアが開いていたので、早速買って帰りました。
風邪といえば葛根湯しか浮かばない私。
で、ネットで検索しました。
まずは、Wikipediaですね。
バクモンドウ
「バクモンドウ(麦門冬)は、ジャノヒゲの根である。」
↓
ジャノヒゲ
「リュウノヒゲ(竜の髯)ともいう。」
あれあれ? (@_@)
うちの庭にもいらっしゃる方でありました。

で、市販されている風邪用の漢方薬も、こんなに種類があったんですね。
知りませんでした。(^^;)
●葛根湯:風邪のひきはじめ
●小青竜湯:鼻水のある風邪
●柴胡桂枝湯:吐き気やお腹にくる風邪
●麻黄湯:悪寒・発熱・関節の痛みのある風邪
●麦門冬湯:たんの切れにくい咳のある風邪
●桔梗湯:のどのはれや痛みのある風邪
たくさんあって迷ったら、薬剤師さんに相談しましょう。
【参考】
ツムラの漢方 かぜ薬シリーズ
クラシエ カンポウ専科 かぜ薬シリーズ
知り合いの方からおすすめされた、のど飴もよさそうです。
カンロ ボイスケアのど飴
必要な時に必要な情報をいただけるのは、本当にありがたいですね。
今後は体力を過信せず、早めの養生を心がけます。
(-人-)~☆
熱や鼻水はなかったのですが、喉がつらい。
痰がからんで咳がひどく、喉を傷めました。
身体はつらくないので、ヨガへ。
エアコンの風で、咳を連発。
すると、森先生から
「気管支を傷めるから、麦門冬湯(ばくもんどうとう)を飲みなさい!!」
とのアドバイスをいただきました。
帰り道、まだドラッグストアが開いていたので、早速買って帰りました。
風邪といえば葛根湯しか浮かばない私。
で、ネットで検索しました。
まずは、Wikipediaですね。
バクモンドウ
「バクモンドウ(麦門冬)は、ジャノヒゲの根である。」
↓
ジャノヒゲ
「リュウノヒゲ(竜の髯)ともいう。」
あれあれ? (@_@)
うちの庭にもいらっしゃる方でありました。

で、市販されている風邪用の漢方薬も、こんなに種類があったんですね。
知りませんでした。(^^;)
●葛根湯:風邪のひきはじめ
●小青竜湯:鼻水のある風邪
●柴胡桂枝湯:吐き気やお腹にくる風邪
●麻黄湯:悪寒・発熱・関節の痛みのある風邪
●麦門冬湯:たんの切れにくい咳のある風邪
●桔梗湯:のどのはれや痛みのある風邪
たくさんあって迷ったら、薬剤師さんに相談しましょう。
【参考】
ツムラの漢方 かぜ薬シリーズ
クラシエ カンポウ専科 かぜ薬シリーズ
知り合いの方からおすすめされた、のど飴もよさそうです。
カンロ ボイスケアのど飴
必要な時に必要な情報をいただけるのは、本当にありがたいですね。
今後は体力を過信せず、早めの養生を心がけます。
(-人-)~☆
2015年09月25日
女性と便秘
女性に多いのが、便秘。
これにはちゃんと根拠があるのだそうです。
●排便に必要な筋力が弱い。
●食物繊維や炭水化物を十分摂取していても、排便を我慢することが多く、排便中枢の反応が抑制されてしまう。
●食事制限が腸の蠕動運動を低下させる。
●女性ホルモン(黄体ホルモンやプロゲステロン)が体内に水分を蓄積しようとし、排便に必要な水分が不足する。
●骨盤腔が広く、腸が下垂し不安定になりやすい。
●下半身に脂肪が溜まりやすく、血液も骨盤に滞りがちになり、腸の働きが低下しやすい。
また、アレルギーやストレスも関連していることもあります。
----------
便は健康状態を反映していると言われていますね。
その内訳は、
水分が60%程度。
次に多いのが、代謝された腸壁細胞の死骸で、15%~20%。
(腸壁細胞の寿命は24時間と短いらしい。)
腸内細菌類の死骸も多く、10%~15%。
食べ物の残滓(のこりかす)は意外に少なく、5%程度なのだそうです。
体内に蓄積していた毒素も排出しますから、排便行為はとても重要です。
便は健康のバロメーター、そして貴重な「体内情報」でもあります。
色・臭い・量・形状など、普段から流す前によく観察しましょう。
お恥ずかしながら、私も実践しております。(^^;)
福助も日々、自分のウンチが流れるのを観察します。

これは本能なのか?
私には謎の行動です。
Φ(?_?)
これにはちゃんと根拠があるのだそうです。
●排便に必要な筋力が弱い。
●食物繊維や炭水化物を十分摂取していても、排便を我慢することが多く、排便中枢の反応が抑制されてしまう。
●食事制限が腸の蠕動運動を低下させる。
●女性ホルモン(黄体ホルモンやプロゲステロン)が体内に水分を蓄積しようとし、排便に必要な水分が不足する。
●骨盤腔が広く、腸が下垂し不安定になりやすい。
●下半身に脂肪が溜まりやすく、血液も骨盤に滞りがちになり、腸の働きが低下しやすい。
また、アレルギーやストレスも関連していることもあります。
----------
便は健康状態を反映していると言われていますね。
その内訳は、
水分が60%程度。
次に多いのが、代謝された腸壁細胞の死骸で、15%~20%。
(腸壁細胞の寿命は24時間と短いらしい。)
腸内細菌類の死骸も多く、10%~15%。
食べ物の残滓(のこりかす)は意外に少なく、5%程度なのだそうです。
体内に蓄積していた毒素も排出しますから、排便行為はとても重要です。
便は健康のバロメーター、そして貴重な「体内情報」でもあります。
色・臭い・量・形状など、普段から流す前によく観察しましょう。
お恥ずかしながら、私も実践しております。(^^;)
福助も日々、自分のウンチが流れるのを観察します。
これは本能なのか?
私には謎の行動です。
Φ(?_?)
2015年09月24日
体幹エクササイズを始めましょう。(中~上級編)
体幹エクササイズ、今度は中~上級編です。
ブリッジのバリエーションになります。
【ポイント】
●1ポーズ30~60秒、無理のない範囲で。
●呼吸は止めないように。
-----------
1.フロントブリッジ
①基本姿勢
●四つ這いになって手足を肩幅に開き、床に対して90度になるようにします。
肘を少し曲げ、身体と床が平行になるように保ちます。
●口から息を吐きながら、おへそを覗き込むように背中を丸めます。

●鼻から息を吸いながら、視線を床に戻して背中を反らせます。

●骨盤の位置を中立位に保ち、下腹部(臍下丹田)に力を入れます。

●身体をまっすぐに保ったまま、床に肘をついて30~60秒キープします。

②膝の位置を後につき、身体を床と並行に保ちます。
③足を伸ばしてつま先と肘で身体を支え、膝を浮かせます。

④③の状態から片足ずつ持ち上げてみましょう。

⑤チャレンジ:④の状態から肘の位置を前に移動してみましょう。
①→⑤と強度が増します。
①がクリアできてから次のステップへ進みましょう。
-----------
2.ショルダーブリッジ
①基本姿勢
●床と腰のすきまに手を入れ、骨盤を前傾させます。

●お腹に手を当て、床に腰が着くように骨盤を中立位に保ちます。

●下腹部(臍下丹田)に力を入れ、てのひらを下に向けて両手を真横に広げます。
●身体をまっすぐに保ったまま、お尻を持ち上げて30~60秒キープします。

②手の位置を身体の横に移動します。

③手を胸の前で組んでみます。

④胸の前でてのひらを合わせて上に伸ばします。
⑤チャレンジ:④の状態から片足ずつ持ち上げてみましょう。

①→⑤と強度が増します。
①がクリアできてから次のステップへ進みましょう。
なお、腰や首などに痛みがある方は無理をしませんよう。
かかりつけの先生に適切なアドバイスをいただいてくださいね。
-----------
さて、中級~上級編は以上です。
いかがだったでしょうか?
身体の前面と後面をバランスよく鍛えるため、フロントブリッジとショルダーブリッジはワンセットで実施してみましょう。
無理のない姿勢で美しいスタイルを目指しましょう。
(-人-)~☆
ブリッジのバリエーションになります。
【ポイント】
●1ポーズ30~60秒、無理のない範囲で。
●呼吸は止めないように。
-----------
1.フロントブリッジ
①基本姿勢
●四つ這いになって手足を肩幅に開き、床に対して90度になるようにします。
肘を少し曲げ、身体と床が平行になるように保ちます。
●口から息を吐きながら、おへそを覗き込むように背中を丸めます。
●鼻から息を吸いながら、視線を床に戻して背中を反らせます。
●骨盤の位置を中立位に保ち、下腹部(臍下丹田)に力を入れます。
●身体をまっすぐに保ったまま、床に肘をついて30~60秒キープします。
②膝の位置を後につき、身体を床と並行に保ちます。
③足を伸ばしてつま先と肘で身体を支え、膝を浮かせます。
④③の状態から片足ずつ持ち上げてみましょう。
⑤チャレンジ:④の状態から肘の位置を前に移動してみましょう。
①→⑤と強度が増します。
①がクリアできてから次のステップへ進みましょう。
-----------
2.ショルダーブリッジ
①基本姿勢
●床と腰のすきまに手を入れ、骨盤を前傾させます。
●お腹に手を当て、床に腰が着くように骨盤を中立位に保ちます。
●下腹部(臍下丹田)に力を入れ、てのひらを下に向けて両手を真横に広げます。
●身体をまっすぐに保ったまま、お尻を持ち上げて30~60秒キープします。
②手の位置を身体の横に移動します。
③手を胸の前で組んでみます。
④胸の前でてのひらを合わせて上に伸ばします。
⑤チャレンジ:④の状態から片足ずつ持ち上げてみましょう。
①→⑤と強度が増します。
①がクリアできてから次のステップへ進みましょう。
なお、腰や首などに痛みがある方は無理をしませんよう。
かかりつけの先生に適切なアドバイスをいただいてくださいね。
-----------
さて、中級~上級編は以上です。
いかがだったでしょうか?
身体の前面と後面をバランスよく鍛えるため、フロントブリッジとショルダーブリッジはワンセットで実施してみましょう。
無理のない姿勢で美しいスタイルを目指しましょう。
(-人-)~☆
2015年09月23日
体幹エクササイズを始めましょう。(初級編)
体幹エクササイズの基本姿勢がマスターできたら、エクササイズを始めてみましょう。
まずは初級編、片足バランスのバリエーション。
股関節まわりは身体の中でも老化が目立つとされています。
特に、足を後ろにあげる「伸展」は、一番可動域が減少しやすいので、日頃から意識して鍛えたいですね。
【ポイント】
●1ポーズ30~60秒、無理のない範囲で。
●呼吸は止めないように。
●左右行います。
-----------
1.椅子で、片足バランス
①椅子に浅めに座ります。
背もたれに寄りかからないようにしましょう。
②膝を曲げたまま、片足ずつ持ち上げます。

③チャレンジ:膝を伸ばしたまま、片足ずつ持ち上げてみましょう。

2.立位で、片足バランス
①足を伸ばしたまま、前方・後方・側方、それぞれの方向に足を持ち上げます。

②膝を曲げて、前方・側方・後方、それぞれの方向に足を持ち上げます。
③チャレンジ:②を一連の動作で行います。
前方→側方→後方
後方→側方→前方
バランスが崩れやすい場合は、椅子につかまりながらでOKです。
なお、膝や腰などに痛みがある方は無理をしませんよう。
かかりつけの先生に適切なアドバイスをいただいてくださいね。
-----------
さて、初級編は以上です。
いかがだったでしょうか?
次回は中級~上級編です。
一緒にがんばりましょう!
(-人-)~☆
まずは初級編、片足バランスのバリエーション。
股関節まわりは身体の中でも老化が目立つとされています。
特に、足を後ろにあげる「伸展」は、一番可動域が減少しやすいので、日頃から意識して鍛えたいですね。
【ポイント】
●1ポーズ30~60秒、無理のない範囲で。
●呼吸は止めないように。
●左右行います。
-----------
1.椅子で、片足バランス
①椅子に浅めに座ります。
背もたれに寄りかからないようにしましょう。
②膝を曲げたまま、片足ずつ持ち上げます。
③チャレンジ:膝を伸ばしたまま、片足ずつ持ち上げてみましょう。
2.立位で、片足バランス
①足を伸ばしたまま、前方・後方・側方、それぞれの方向に足を持ち上げます。
②膝を曲げて、前方・側方・後方、それぞれの方向に足を持ち上げます。
③チャレンジ:②を一連の動作で行います。
前方→側方→後方
後方→側方→前方
バランスが崩れやすい場合は、椅子につかまりながらでOKです。
なお、膝や腰などに痛みがある方は無理をしませんよう。
かかりつけの先生に適切なアドバイスをいただいてくださいね。
-----------
さて、初級編は以上です。
いかがだったでしょうか?
次回は中級~上級編です。
一緒にがんばりましょう!
(-人-)~☆
2015年09月22日
体幹エクササイズの基本姿勢
「体幹」は、読んで字のごとく「体の幹」、胴体部分を指します。
身体のコア(中心)となる部分です。
人間の身体の頭部と四肢(左右の手足)を除いた部分。
お腹周りだけでなく、背中や腰周りも含めた胴体の中心部全体と考えていただければよいと思います。
体幹エクササイズの時に重要なのが、基本姿勢です。
しっかり身につけましょう。
骨盤を中間位に保ち、腹圧を高め、ドローインをキープした状態です。
では、さっそく実践してみましょう。
----------
【骨盤の中間位】
①両手を腰に当て、骨盤が後ろに傾くように動かす。
②骨盤を前に傾けるように動かす
③骨盤を前後に10回程度動かし、中間の位置で止める。
こちらは座位で行うのもおすすめです。
坐骨を意識して座ると、骨盤の動きがわかりやすいと思います。
【腹圧】
①鼻から息を吸いながら、両手を挙げ、同時にお腹を引っ込める。
②両手を身体の真横に下ろす。
③この状態をキープする。
呼吸を意識するには仰向けもおすすめです。
膝を軽く曲げるとさらにお腹を意識しやすくなります。
みぞおちを引っ込めてからへそを引っ込めると、お腹全体が引っ込みやすいでしょう。
【ドローイン】
へそ下3~5cmの場所を「臍下丹田(せいかたんでん)」と呼び、ここへ力を込めることをドローインといいます。
①骨盤を中間位に保ちます。
②腹圧を高めます。
③ドローインします。
----------
どうでしょう?
うまくできましたか?
すぐには難しいかもしれません。
でも少しずつ続けてください。
継続することが重要です。
お仕事中にもトレーニング可能です。

なお、腰痛のある方は無理をしませんよう。
かかりつけの先生に適切なアドバイスをいただいてくださいね。
(-人-)~☆
身体のコア(中心)となる部分です。
人間の身体の頭部と四肢(左右の手足)を除いた部分。
お腹周りだけでなく、背中や腰周りも含めた胴体の中心部全体と考えていただければよいと思います。
体幹エクササイズの時に重要なのが、基本姿勢です。
しっかり身につけましょう。
骨盤を中間位に保ち、腹圧を高め、ドローインをキープした状態です。
では、さっそく実践してみましょう。
----------
【骨盤の中間位】
①両手を腰に当て、骨盤が後ろに傾くように動かす。
②骨盤を前に傾けるように動かす
③骨盤を前後に10回程度動かし、中間の位置で止める。
こちらは座位で行うのもおすすめです。
坐骨を意識して座ると、骨盤の動きがわかりやすいと思います。
【腹圧】
①鼻から息を吸いながら、両手を挙げ、同時にお腹を引っ込める。
②両手を身体の真横に下ろす。
③この状態をキープする。
呼吸を意識するには仰向けもおすすめです。
膝を軽く曲げるとさらにお腹を意識しやすくなります。
みぞおちを引っ込めてからへそを引っ込めると、お腹全体が引っ込みやすいでしょう。
【ドローイン】
へそ下3~5cmの場所を「臍下丹田(せいかたんでん)」と呼び、ここへ力を込めることをドローインといいます。
①骨盤を中間位に保ちます。
②腹圧を高めます。
③ドローインします。
----------
どうでしょう?
うまくできましたか?
すぐには難しいかもしれません。
でも少しずつ続けてください。
継続することが重要です。
お仕事中にもトレーニング可能です。
なお、腰痛のある方は無理をしませんよう。
かかりつけの先生に適切なアドバイスをいただいてくださいね。
(-人-)~☆
2015年09月21日
体幹(コア)を意識して、肚を据える
トレーニングで重要な事。
それは体幹(コア)を意識することです。
体幹とは、人の胴体部分のことです。
身体の中心を指し、コアともいいます。
体幹を取り巻く筋肉は、大きく深層筋と表層筋の2つに分けられます。
深層部の筋肉は内側から、表層部の筋肉は外側から、体幹を安定させるために働いています。
先日のセミナーで改めて体感したこと。
それは
「筋肉は、深層から浅層へと働く」
ということです。
腹部を取り囲む主な深層筋は以下の4つです。(諸説ありますが。)
・横隔膜:
・腹横筋:
・骨盤底筋:
・多裂筋:
体幹の機能が向上すると、内臓を正しい位置に安定でき、正常に機能させることが可能になります。
また正しい姿勢を維持できることで、肩や腰などの負担が軽減ができます。
このため、日常動作やスポーツ等での動きがスムーズに安定して行えるようになります。
個人的には
「肚が据わる」
という言葉がしっくりきます。
体の中に軸がてきる感じです。
----------
CMなんか見ていると、筋骨隆々なモデルさんが出てきます。
「かっこいいなぁ!」
と思いますが、表面的な筋肉=表層筋なのです。
見た目が良いだけで、実際には「使えない」筋肉っていうのもあるわけです。
お顔で考えると、お化粧ですね。(^^;)
でも、素肌が美しくないと、お化粧もいまひとつ映えません。
コアを意識できた上で、表層の筋肉を鍛えていくと、「使える筋肉」が増やせます。
ですから、まずは体幹をうまくコントロールできるようになりましょう。
運動の秋ですね。
ぜひ、コアトレーニングにチャレンジしてみませんか?
(-人-)~☆

karada+ の馬場大輔先生と渡邉申也先生です。
お2人ともコアを鍛えた、素敵な「細マッチョ」でした。(^^)
それは体幹(コア)を意識することです。
体幹とは、人の胴体部分のことです。
身体の中心を指し、コアともいいます。
体幹を取り巻く筋肉は、大きく深層筋と表層筋の2つに分けられます。
深層部の筋肉は内側から、表層部の筋肉は外側から、体幹を安定させるために働いています。
先日のセミナーで改めて体感したこと。
それは
「筋肉は、深層から浅層へと働く」
ということです。
腹部を取り囲む主な深層筋は以下の4つです。(諸説ありますが。)
・横隔膜:
・腹横筋:
・骨盤底筋:
・多裂筋:
体幹の機能が向上すると、内臓を正しい位置に安定でき、正常に機能させることが可能になります。
また正しい姿勢を維持できることで、肩や腰などの負担が軽減ができます。
このため、日常動作やスポーツ等での動きがスムーズに安定して行えるようになります。
個人的には
「肚が据わる」
という言葉がしっくりきます。
体の中に軸がてきる感じです。
----------
CMなんか見ていると、筋骨隆々なモデルさんが出てきます。
「かっこいいなぁ!」
と思いますが、表面的な筋肉=表層筋なのです。
見た目が良いだけで、実際には「使えない」筋肉っていうのもあるわけです。
お顔で考えると、お化粧ですね。(^^;)
でも、素肌が美しくないと、お化粧もいまひとつ映えません。
コアを意識できた上で、表層の筋肉を鍛えていくと、「使える筋肉」が増やせます。
ですから、まずは体幹をうまくコントロールできるようになりましょう。
運動の秋ですね。
ぜひ、コアトレーニングにチャレンジしてみませんか?
(-人-)~☆
karada+ の馬場大輔先生と渡邉申也先生です。
お2人ともコアを鍛えた、素敵な「細マッチョ」でした。(^^)