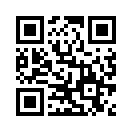2017年10月20日
免疫の低下と膀胱炎
不安定な天気が続きますね。
気温の変化も急激です。
このような環境では、体温を調節する自律神経のバランスが乱れがちになります。
すると、免疫力の低下につながってしまうのです。
----------
ここのところ、「膀胱炎にかかった」とおっしゃる方が数人いらっしゃいました。
膀胱炎は、尿道口から細菌が侵入して、炎症を起こすもの。
通常であれば、排尿や免疫機構によって膀胱炎には至りません。
ところが、疲れやストレスなどで体の抵抗力が落ちると、菌が感染・増殖して急性膀胱炎を発症することがあります。
頻尿、排尿時の痛み、尿の混濁などがあるときは、早めに病院を受診しましょう。
内科・婦人科・泌尿器科で対応してくれます。
症状が長引いたり、何度も膀胱炎になる場合は、専門の泌尿器科の受診が良いでしょう。
----------
予防には、泌尿器を清潔に保つことがあげられますが、ビデの使いすぎは注意が必要だそう。
そして、自律神経のバランスを整えるには、カイロプラクティックも有効です。
カイロ・ウノでも微力ながら、そのお手伝いをさせていただいております。
(-人-)~☆
気温の変化も急激です。
このような環境では、体温を調節する自律神経のバランスが乱れがちになります。
すると、免疫力の低下につながってしまうのです。
----------
ここのところ、「膀胱炎にかかった」とおっしゃる方が数人いらっしゃいました。
膀胱炎は、尿道口から細菌が侵入して、炎症を起こすもの。
通常であれば、排尿や免疫機構によって膀胱炎には至りません。
ところが、疲れやストレスなどで体の抵抗力が落ちると、菌が感染・増殖して急性膀胱炎を発症することがあります。
頻尿、排尿時の痛み、尿の混濁などがあるときは、早めに病院を受診しましょう。
内科・婦人科・泌尿器科で対応してくれます。
症状が長引いたり、何度も膀胱炎になる場合は、専門の泌尿器科の受診が良いでしょう。
----------
予防には、泌尿器を清潔に保つことがあげられますが、ビデの使いすぎは注意が必要だそう。
そして、自律神経のバランスを整えるには、カイロプラクティックも有効です。
カイロ・ウノでも微力ながら、そのお手伝いをさせていただいております。
(-人-)~☆
2017年10月20日
ドミノ骨折の予防をしましょう。
10月10日といえば、昔は「体育の日」。
今では、「転倒予防の日」だそうです。
また日本整形外科学会は、10月を「骨と関節の月間」として、骨の健康を保ち、骨折を防ぐことの大切さを訴えています。
----------
先日、テレビを見ていたら、「ドミノ骨折」の文字が…。
ドミノ骨折とは、1回の骨折が引き金となって、その後、相次いで骨折すること。
怖いですね。(;_;)
高齢者に多く、日常生活に大きな影響がでるおそれがあるため、注意が必要です。
ドミノ骨折を予防するには、骨を丈夫に保つ栄養を摂るのが有効。
骨粗しょう症の予防にも効果的です。
----------
まずは、カルシウム。
次に、骨の形成を促進するビタミンKで、多いのは納豆(特にひきわり納豆)だそう。
そして、カルシウムの吸収を促進するビタミンDで、キノコや魚。
また、1日30分の日光浴も、ビタミンD生成に良いそうです。
いくつになっても骨を丈夫に保って、元気に過ごしたいものですね。
(-人-)~☆
今では、「転倒予防の日」だそうです。
また日本整形外科学会は、10月を「骨と関節の月間」として、骨の健康を保ち、骨折を防ぐことの大切さを訴えています。
----------
先日、テレビを見ていたら、「ドミノ骨折」の文字が…。
ドミノ骨折とは、1回の骨折が引き金となって、その後、相次いで骨折すること。
怖いですね。(;_;)
高齢者に多く、日常生活に大きな影響がでるおそれがあるため、注意が必要です。
ドミノ骨折を予防するには、骨を丈夫に保つ栄養を摂るのが有効。
骨粗しょう症の予防にも効果的です。
----------
まずは、カルシウム。
次に、骨の形成を促進するビタミンKで、多いのは納豆(特にひきわり納豆)だそう。
そして、カルシウムの吸収を促進するビタミンDで、キノコや魚。
また、1日30分の日光浴も、ビタミンD生成に良いそうです。
いくつになっても骨を丈夫に保って、元気に過ごしたいものですね。
(-人-)~☆
2017年06月04日
師匠 増田 裕先生(カイロプラクティック)
友人が「カイロジャーナル」を携えて、三島に来た。
カイロジャーナルは、科学新聞社から年3回発行される。
カイロプラクティックやオステオパシーなどの手技療法の最新情報新聞。
増田先生のことが載っていた記事を見つけて、持ってきてくれたのだ。
●安保徹氏のご逝去を悼む(カイロジャーナル88号 (2017.2.19発行))
増田先生は、私の前職(増田カイロプラクティックセンター)の院長。
RMIT卒業後、私は3年ほどセンターでお世話になった。
ネットで検索してみると、業界の生き字引である斉藤さんの5月22日付ブログが見つかった。
●斎藤信次残日録 其の十三『レジェンド 増田さん』
写真ではあるが、久々に元気なお顔を拝見することができ、嬉しかった。
増田先生と初めてお会いしてから、10年以上。
アクティベータ、カイロプラクティック神経学、NAETから哲学的なことまで。
直接あるいは間接的に、本当にいろいろな事を教えていただきました。
今の私があるのは、確実に増田先生のお陰です。
(-人-)~☆

カイロジャーナルは、科学新聞社から年3回発行される。
カイロプラクティックやオステオパシーなどの手技療法の最新情報新聞。
増田先生のことが載っていた記事を見つけて、持ってきてくれたのだ。
●安保徹氏のご逝去を悼む(カイロジャーナル88号 (2017.2.19発行))
増田先生は、私の前職(増田カイロプラクティックセンター)の院長。
RMIT卒業後、私は3年ほどセンターでお世話になった。
ネットで検索してみると、業界の生き字引である斉藤さんの5月22日付ブログが見つかった。
●斎藤信次残日録 其の十三『レジェンド 増田さん』
写真ではあるが、久々に元気なお顔を拝見することができ、嬉しかった。
増田先生と初めてお会いしてから、10年以上。
アクティベータ、カイロプラクティック神経学、NAETから哲学的なことまで。
直接あるいは間接的に、本当にいろいろな事を教えていただきました。
今の私があるのは、確実に増田先生のお陰です。
(-人-)~☆

2016年09月15日
ご存知でしたか?自然欠乏症候群(Nature Deficiency Syndrome)
先日、朝霧高原の日月倶楽部で開催されたリトリートに参加してきました。
日月倶楽部は約20,000坪の雄大な自然環境!
東京ドーム約1.5個分 の広大な敷地にあります。
の広大な敷地にあります。
日月倶楽部では、ヨガや瞑想などのマインドフルネス、企業の健康管理者への指導、健康関連分野のセミナー合宿など、雄大な自然環境に身を置いて行う各種滞在プログラムを提供しています。
代表は、山本竜隆(やまもと たつたか)先生。
朝霧高原診療所で診療をしながら、「自然欠乏症候群」の提唱活動をしていらっしゃいます。
今回、山本先生から「自然欠乏症候群(Nature Deficiency Syndrome)」について、お話を伺うことができました。
----------
自然欠乏症候群(Nature Deficiency Syndrome)という言葉、ご存知でしたか?
欧米では10年ほど前から話題になっているそうです。
きっかけは2005年にアメリカで出版された本。
"Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder"
邦題「あなたの 子どもに自然が足りない」


著者のリチャード・ルーブは、多数の専門家の声を紹介しながら、子どもの成長には自然に触れることが不可欠としています。
最近の研究では、自然の中で遊ぶ経験の少ない子に、自閉症や学習障害などの発達障害が多いことが指摘されているそうです。
ネットで調べてみると、文部科学省では、2015年5月1日の時点で調査を実施しています。
平成25年度通級による指導実施状況調査結果 (PDF:193KB)
発達障害により通級指導を受けている子が、20年あまりの間に7.4倍と急増していました。
この数字には、驚かされます。
大人の場合は、生活習慣病やうつの発症率が高くなります。
これは、自然が足りない都会の人に多くみられる傾向があるようです。
医学の父であるヒポクラテスが
「自然から遠ざかるほど病気に近づく」
という言葉を残しています。
病気ではないけれど、不眠や慢性疲労などに悩まされているという方。
その原因が「自然から遠ざかっている」ことにあるとしたら…。
まずは身近な自然に触れることで、解決の糸口が見つかるかもしれません。
(-人-)~☆


日月倶楽部は約20,000坪の雄大な自然環境!
東京ドーム約1.5個分
 の広大な敷地にあります。
の広大な敷地にあります。日月倶楽部では、ヨガや瞑想などのマインドフルネス、企業の健康管理者への指導、健康関連分野のセミナー合宿など、雄大な自然環境に身を置いて行う各種滞在プログラムを提供しています。
代表は、山本竜隆(やまもと たつたか)先生。
朝霧高原診療所で診療をしながら、「自然欠乏症候群」の提唱活動をしていらっしゃいます。
今回、山本先生から「自然欠乏症候群(Nature Deficiency Syndrome)」について、お話を伺うことができました。
----------
自然欠乏症候群(Nature Deficiency Syndrome)という言葉、ご存知でしたか?
欧米では10年ほど前から話題になっているそうです。
きっかけは2005年にアメリカで出版された本。
"Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder"
邦題「あなたの 子どもに自然が足りない」

著者のリチャード・ルーブは、多数の専門家の声を紹介しながら、子どもの成長には自然に触れることが不可欠としています。
最近の研究では、自然の中で遊ぶ経験の少ない子に、自閉症や学習障害などの発達障害が多いことが指摘されているそうです。
ネットで調べてみると、文部科学省では、2015年5月1日の時点で調査を実施しています。
平成25年度通級による指導実施状況調査結果 (PDF:193KB)
発達障害により通級指導を受けている子が、20年あまりの間に7.4倍と急増していました。
この数字には、驚かされます。
大人の場合は、生活習慣病やうつの発症率が高くなります。
これは、自然が足りない都会の人に多くみられる傾向があるようです。
医学の父であるヒポクラテスが
「自然から遠ざかるほど病気に近づく」
という言葉を残しています。
病気ではないけれど、不眠や慢性疲労などに悩まされているという方。
その原因が「自然から遠ざかっている」ことにあるとしたら…。
まずは身近な自然に触れることで、解決の糸口が見つかるかもしれません。
(-人-)~☆

2016年07月06日
「BUFF BONES®」を体験してきました。
沼津のPILATES BODY STUDIOで、「BUFF BONES®」を体験してきました。
女性にとって、骨の健康はとても重要かつ切実です。
骨粗しょう症が出はじめるのは40代。
しかし、骨密度のピークは、なんと18歳!
ということは、その後は下がる一方…。
ガ━(゚д゚;)━ン!!
骨を強化するには
1.体重負荷
2.抵抗
3.インパクト
が必要となります。
buff は「鍛える」とか「磨く」といった意味。
BUFF BONES = 「骨を鍛える」
「鍛えれば、骨も強くなる」わけですね!
素敵なネーミングです。
「BUFF BONES®」では、
立位→仰向け→うつ伏せ→横向きと体勢を変えながら、
腕・背中・腹筋・股関節・臀筋の調子を整えつつ、計算された無理のない強度で体を動かします。
50分の体験はあっという間でした。
ピラティス初心者の私でも、大丈夫(←自己評価)。(^^;)
骨粗鬆症や骨減少症の方も、安心して参加できるプログラムとなっています。
7月中は、筋膜ストレッチの内容も!
櫻井 淳子さんがインストラクターとしてクラスを開講しています。
是非、体験してみてはいかがでしょう?
PILATES BODY STUDIO ホームページ
女性にとって、骨の健康はとても重要かつ切実です。
骨粗しょう症が出はじめるのは40代。
しかし、骨密度のピークは、なんと18歳!
ということは、その後は下がる一方…。
ガ━(゚д゚;)━ン!!
骨を強化するには
1.体重負荷
2.抵抗
3.インパクト
が必要となります。
buff は「鍛える」とか「磨く」といった意味。
BUFF BONES = 「骨を鍛える」
「鍛えれば、骨も強くなる」わけですね!
素敵なネーミングです。
「BUFF BONES®」では、
立位→仰向け→うつ伏せ→横向きと体勢を変えながら、
腕・背中・腹筋・股関節・臀筋の調子を整えつつ、計算された無理のない強度で体を動かします。
50分の体験はあっという間でした。
ピラティス初心者の私でも、大丈夫(←自己評価)。(^^;)
骨粗鬆症や骨減少症の方も、安心して参加できるプログラムとなっています。
7月中は、筋膜ストレッチの内容も!
櫻井 淳子さんがインストラクターとしてクラスを開講しています。
是非、体験してみてはいかがでしょう?
PILATES BODY STUDIO ホームページ
2016年04月03日
完全呼吸法とヨガ
ヨガでは呼吸法をプラナヤマ(pranayama)といいます。
が、実は単なる呼吸法ではないのだそう。
プラナヤマは、prana と yama の合成語。
プラナ(生命エネルギー)をヤマ(コントロール)する。
広義では食べものや意識も含まれます。
沖ヨガではプラナヤマのことを「調気活用法」といいます。
----------
さて、完全呼吸法についてです。
完全呼吸法は、呼吸筋や肋骨の動きを活性化します。
また横隔膜が上下することで、内臓の活性化にも効果的です。
完全呼吸法は、腹式→胸式→肩(または鎖骨)呼吸を連続して行います。
間にクンバク(息を止める)をはさんで、プラナを身体に留め身体の隅々に行き渡らせましょう。
細胞が目覚めます。 "(@_@)"
【完全呼吸法】
1.まずは、息を吐ききります。
下腹部(丹田)を意識して、ゆっくりと息を吐いていきます。
2.息を吸います。
息は、ゆっくりと鼻から一定に吸いましょう。
プラナが「丹田→肺→胸→気管支」 の順に流れていくのを意識します。
鎖骨呼吸で、下腹部は自然に少し凹みます。
3.息を止める(クンバク)
※血圧の高い方は、クンバクによって血圧が上がることがありますので、注意が必要です。
※クンバクをとばして、4へ進んでください。
みぞおち・丹田に力を集中し、肛門を締めます。
肩の力を抜きます。
プラナが身体に満ち、全身に流れていくのをイメージしましょう。
4.息を吐く
ゆっくりと息を吐きます。
胸の位置を維持しながら、腹をへこませながら息を吐いていきます。
さらに胸を元に戻しながら吐き、続けて肩を下げながら吐きます。
空気が完全になくなったら、胸とお腹をリラックスさせます。
1~3を一連の流れで繰り返します。
自然に出来るようになると良いですね。
片方の手を丹田に、もう片方の手を胸の上にあてると、お腹と胸の動きが分かりやすいです。
呼吸の長さは、吸う:クンバク:吐くを1サイクルとして
● 最初は、 1:1:1
● 慣れたら、1:2:2
● さらに、 1:4:2
の割合になるように伸ばしていきましょう。
肺は「意識的にコントロールできる唯一の臓器」といわれています。
呼吸で身体をリラックスさせ、副交感神経のスイッチを入れましょう。
疲労回復にも効果的!!
ぜひ、お試しくださいませ。
(-人-)~☆

が、実は単なる呼吸法ではないのだそう。
プラナヤマは、prana と yama の合成語。
プラナ(生命エネルギー)をヤマ(コントロール)する。
広義では食べものや意識も含まれます。
沖ヨガではプラナヤマのことを「調気活用法」といいます。
----------
さて、完全呼吸法についてです。
完全呼吸法は、呼吸筋や肋骨の動きを活性化します。
また横隔膜が上下することで、内臓の活性化にも効果的です。
完全呼吸法は、腹式→胸式→肩(または鎖骨)呼吸を連続して行います。
間にクンバク(息を止める)をはさんで、プラナを身体に留め身体の隅々に行き渡らせましょう。
細胞が目覚めます。 "(@_@)"
【完全呼吸法】
1.まずは、息を吐ききります。
下腹部(丹田)を意識して、ゆっくりと息を吐いていきます。
2.息を吸います。
息は、ゆっくりと鼻から一定に吸いましょう。
プラナが「丹田→肺→胸→気管支」 の順に流れていくのを意識します。
鎖骨呼吸で、下腹部は自然に少し凹みます。
3.息を止める(クンバク)
※血圧の高い方は、クンバクによって血圧が上がることがありますので、注意が必要です。
※クンバクをとばして、4へ進んでください。
みぞおち・丹田に力を集中し、肛門を締めます。
肩の力を抜きます。
プラナが身体に満ち、全身に流れていくのをイメージしましょう。
4.息を吐く
ゆっくりと息を吐きます。
胸の位置を維持しながら、腹をへこませながら息を吐いていきます。
さらに胸を元に戻しながら吐き、続けて肩を下げながら吐きます。
空気が完全になくなったら、胸とお腹をリラックスさせます。
1~3を一連の流れで繰り返します。
自然に出来るようになると良いですね。
片方の手を丹田に、もう片方の手を胸の上にあてると、お腹と胸の動きが分かりやすいです。
呼吸の長さは、吸う:クンバク:吐くを1サイクルとして
● 最初は、 1:1:1
● 慣れたら、1:2:2
● さらに、 1:4:2
の割合になるように伸ばしていきましょう。
肺は「意識的にコントロールできる唯一の臓器」といわれています。
呼吸で身体をリラックスさせ、副交感神経のスイッチを入れましょう。
疲労回復にも効果的!!
ぜひ、お試しくださいませ。
(-人-)~☆
2016年03月27日
内転筋の痛みと感情
昨日いらっしゃったクライアント様。
予約の時、「股関節を痛めたかも。」とおっしゃいます。
問診では、明らかにスポーツ中に発生した痛み。
触診させていただくと、内転筋(大内転筋)に限局した痛みの部位が確認できました。
痛み自体は初日よりもかなり軽減しているとのこと。
炎症反応もなく経過も順調でしたので、施術は可能と判断しました。
筋力検査から、施術は足首→骨盤→首→内転筋の順に決定。
足首についてクライアント様にたずねると、
「左足首の冷えは2週間前から気になっていた」
とのこと。
施術中に会話をしていくと、
「私の考えは、他の方にほとんど理解してもらえないんですよ。」
「間違いなく、お役にたてるはずなのに…。」
とおっしゃいます。
感情も関係していると、容易に予想できます。
内転筋は東洋医学で心包系と関連付けられます。
精神的な苦痛、今回の場合「自分を無価値ととらえる」ことで、筋力が弱化していた可能性があります。
TMS(Tension Myositis Syndrome)理論を提唱するジョン・サーノ博士は、CNNの番組で
----------
痛みを生み出しているのは自分自身であり、もちろん無意識のうちにです。
ストレスや怒り、恐怖に対する心の反応がそうさせます。
怒りに向き合うくらいならと、体のある部分への血流を減らして、そちらへ注意を引きつけようとします。
その結果、腰なり首なり足関節なり、痛みが生じることで、怒りなどの受け入れがたい感情から注意がそらされるのです。
----------
といっています。
このように、体だけに向き合っているとわからない、感情という名のブラックボックス。
早めのケアで、身体症状の速やかな改善が期待できます。
もちろん、治すのは患者さん自身が持つ自然治癒力。
カイロ・ウノではそのお手伝いをさせていただいております。
(-人-)~☆

予約の時、「股関節を痛めたかも。」とおっしゃいます。
問診では、明らかにスポーツ中に発生した痛み。
触診させていただくと、内転筋(大内転筋)に限局した痛みの部位が確認できました。
痛み自体は初日よりもかなり軽減しているとのこと。
炎症反応もなく経過も順調でしたので、施術は可能と判断しました。
筋力検査から、施術は足首→骨盤→首→内転筋の順に決定。
足首についてクライアント様にたずねると、
「左足首の冷えは2週間前から気になっていた」
とのこと。
施術中に会話をしていくと、
「私の考えは、他の方にほとんど理解してもらえないんですよ。」
「間違いなく、お役にたてるはずなのに…。」
とおっしゃいます。
感情も関係していると、容易に予想できます。
内転筋は東洋医学で心包系と関連付けられます。
精神的な苦痛、今回の場合「自分を無価値ととらえる」ことで、筋力が弱化していた可能性があります。
TMS(Tension Myositis Syndrome)理論を提唱するジョン・サーノ博士は、CNNの番組で
----------
痛みを生み出しているのは自分自身であり、もちろん無意識のうちにです。
ストレスや怒り、恐怖に対する心の反応がそうさせます。
怒りに向き合うくらいならと、体のある部分への血流を減らして、そちらへ注意を引きつけようとします。
その結果、腰なり首なり足関節なり、痛みが生じることで、怒りなどの受け入れがたい感情から注意がそらされるのです。
----------
といっています。
このように、体だけに向き合っているとわからない、感情という名のブラックボックス。
早めのケアで、身体症状の速やかな改善が期待できます。
もちろん、治すのは患者さん自身が持つ自然治癒力。
カイロ・ウノではそのお手伝いをさせていただいております。
(-人-)~☆
2016年03月18日
イップスにtDCS(経頭蓋直流電気刺激)
NHK教育テレビの「サイエンスZERO」。
前回は「電気刺激で“脳”力アップ!脳刺激研究最前線」というタイトルでした。
録画してみると、tDCS(経頭蓋直流電気刺激)についての内容でした。
----------
脳の力をアップする。
ドイツやアメリカを中心に今、画期的な治療法が注目を集めている。
脳に電気刺激を与えて、脳の活動を“操る”「tDCS」と呼ばれる手法だ。
頭の表面に微弱な電流を流すことで、運動野や言語野などが刺激され、脳の活動を高めるのだ。
応用が進んでいるのが医療分野。
脳卒中の後遺症やうつ病などの脳疾患を治療する装置として臨床試験が行われ、効果が報告されている。
ドイツの事例を中心に最先端技術に迫る。
----------
【引用】NHKサイエンスZERO「電気刺激で“脳”力アップ!脳刺激研究最前線」
番組内では、局所性ジストニアを取り上げていました。
局所性ジストニアは、同じ動作を職業的に繰り返すことで、意図しない動きが起こる病気。
例えばピアニストの場合、通常は指を上下に動かしますが、意図せずに指が巻き込んでしまうそう。
根本的な治療法はありません。
これは、脳の可塑性が関連しているようです。
可塑性はうまく引き出すことで、リハビリや学習効率が良くなると考えられます。
しかし、動作を繰り返すことによって、自分の意図していない可塑性が引き出されることがあるのです。
Φ(@_@)
左脳と右脳の情報交換は脳梁を通しておこなわれます。
tDCSは、情報の流れを制御します。
陽極側を目的部位に設置すれば直下の皮質の興奮が促進され、陰極側であれば皮質の興奮が抑制されます。
これを治療に利用します。
tDCSは、イップス(Yips)にも有効と考えられています。
イップスは
「精神的な原因などによりスポーツの動作に支障をきたし、自分の思い通りのプレーができなくなる運動障害」
とされてきました。
しかし、精神的な物ではなく、脳の可塑性が関係しているかもしれません。
以前、TMS(Transcranial Magnetic Stimulation; 経頭蓋磁気刺激)を扱った番組をみました。
【過去ブログ】
TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)
http://blog.goo.ne.jp/chirosano/e/8b75ab440f540ef0f364638a1c61ae7d
tDCSとTMSの違いは、刺激に電気を用いるか磁気かという点。
また、tDCSはTMSに比べて機材が安価で、被験者に負担が少なく、持ち運びが容易だそう。
まだ研究中とのことですが、多方面へ応用が可能らしい。
今後に期待したいですね。
(-人-)~☆

前回は「電気刺激で“脳”力アップ!脳刺激研究最前線」というタイトルでした。
録画してみると、tDCS(経頭蓋直流電気刺激)についての内容でした。
----------
脳の力をアップする。
ドイツやアメリカを中心に今、画期的な治療法が注目を集めている。
脳に電気刺激を与えて、脳の活動を“操る”「tDCS」と呼ばれる手法だ。
頭の表面に微弱な電流を流すことで、運動野や言語野などが刺激され、脳の活動を高めるのだ。
応用が進んでいるのが医療分野。
脳卒中の後遺症やうつ病などの脳疾患を治療する装置として臨床試験が行われ、効果が報告されている。
ドイツの事例を中心に最先端技術に迫る。
----------
【引用】NHKサイエンスZERO「電気刺激で“脳”力アップ!脳刺激研究最前線」
番組内では、局所性ジストニアを取り上げていました。
局所性ジストニアは、同じ動作を職業的に繰り返すことで、意図しない動きが起こる病気。
例えばピアニストの場合、通常は指を上下に動かしますが、意図せずに指が巻き込んでしまうそう。
根本的な治療法はありません。
これは、脳の可塑性が関連しているようです。
可塑性はうまく引き出すことで、リハビリや学習効率が良くなると考えられます。
しかし、動作を繰り返すことによって、自分の意図していない可塑性が引き出されることがあるのです。
Φ(@_@)
左脳と右脳の情報交換は脳梁を通しておこなわれます。
tDCSは、情報の流れを制御します。
陽極側を目的部位に設置すれば直下の皮質の興奮が促進され、陰極側であれば皮質の興奮が抑制されます。
これを治療に利用します。
tDCSは、イップス(Yips)にも有効と考えられています。
イップスは
「精神的な原因などによりスポーツの動作に支障をきたし、自分の思い通りのプレーができなくなる運動障害」
とされてきました。
しかし、精神的な物ではなく、脳の可塑性が関係しているかもしれません。
以前、TMS(Transcranial Magnetic Stimulation; 経頭蓋磁気刺激)を扱った番組をみました。
【過去ブログ】
TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)
http://blog.goo.ne.jp/chirosano/e/8b75ab440f540ef0f364638a1c61ae7d
tDCSとTMSの違いは、刺激に電気を用いるか磁気かという点。
また、tDCSはTMSに比べて機材が安価で、被験者に負担が少なく、持ち運びが容易だそう。
まだ研究中とのことですが、多方面へ応用が可能らしい。
今後に期待したいですね。
(-人-)~☆

2016年03月06日
「シナプソロジー」を体験してきました。
先日、シナプソロジーを体験してきました。
シナプソロジーとは、
----------
脳を活性化させるには、脳に適度な刺激を繰り返し与えることが必要で、楽しく、意欲的に行うことで、更に効果的になると言われています。
シナプソロジーは、「2つのことを同時に行う」「左右で違う動きをする」といった普段慣れない動きで脳を適度に混乱させ、さらに効果的な刺激を与えることで、脳の機能が高められると考えられています。
笑顔やコミュニケーションが生まれるので、楽しく続けられるのが特徴です。
----------
引用: シナプソロジー普及協会
たとえば「スリスリトントン」というプログラム
(1)椅子に座ります。
(2)両手を机や太腿の上に置きます。
(3)片手は「スリスリ」、片手は握りこぶしをつくって「トントン」と、左右で違う動きをします。
こんな感じ。


(4)左右を変えます。
できるようになったら、さらに動きに変化をつけます。
ゲームだとレベルアップとかいいますが、シナプソロジーではスパイスアップ(刺激の変化)と呼びます。
(5)自分の前に壁があるのをイメージして、(3)(4)を行います。
(6)自分の左右に壁があるのをイメージして、(3)(4)を行います。
どうですか?
上手くできましたか??
私、スパイスアップの(5)が上手くできず、「イラッ」とか「モヤッ」としました。
でも、この感覚が脳に刺激として有効のようです。
繰り返しやっていくと、かなり上達?しましたよ。
通常あまりしない動きをすることは、脳の活性化につながるようです。
ぜひチャレンジしてみてください!
シナプソロジーとは、
----------
脳を活性化させるには、脳に適度な刺激を繰り返し与えることが必要で、楽しく、意欲的に行うことで、更に効果的になると言われています。
シナプソロジーは、「2つのことを同時に行う」「左右で違う動きをする」といった普段慣れない動きで脳を適度に混乱させ、さらに効果的な刺激を与えることで、脳の機能が高められると考えられています。
笑顔やコミュニケーションが生まれるので、楽しく続けられるのが特徴です。
----------
引用: シナプソロジー普及協会
たとえば「スリスリトントン」というプログラム
(1)椅子に座ります。
(2)両手を机や太腿の上に置きます。
(3)片手は「スリスリ」、片手は握りこぶしをつくって「トントン」と、左右で違う動きをします。
こんな感じ。

(4)左右を変えます。
できるようになったら、さらに動きに変化をつけます。
ゲームだとレベルアップとかいいますが、シナプソロジーではスパイスアップ(刺激の変化)と呼びます。
(5)自分の前に壁があるのをイメージして、(3)(4)を行います。
(6)自分の左右に壁があるのをイメージして、(3)(4)を行います。
どうですか?
上手くできましたか??
私、スパイスアップの(5)が上手くできず、「イラッ」とか「モヤッ」としました。
でも、この感覚が脳に刺激として有効のようです。
繰り返しやっていくと、かなり上達?しましたよ。
通常あまりしない動きをすることは、脳の活性化につながるようです。
ぜひチャレンジしてみてください!
2016年02月09日
夜中の両足の踵(かかと)の痛み
先月いらっしゃったクライアント様。
「両足の踵(かかと)が痛いんです。」
とおっしゃいます。
ある日、夜に両足の踵が痛くて目がさめたそうです。
その日以降、夜になると決まって痛くなって、目がさめる…。
夜、睡眠を邪魔される
心配で、定期的に通っている整形外科でみてもらったが、
「異常はありませんね。」
といわれたそうです。
足底腱膜炎を考えたのですが、触診からも除外してもよさそうです。
夜間のみの痛みということでしたので、次回に経過を教えていただくことに。
先日、経過を伺うと
「痛み、消えました!」
と晴れやかな表情に。
そして
「原因、何だったんですかね?」
と聞かれました。
睡眠中に出てくることから、筋骨格系の刺激が低下することに起因するのだろうと推測できます。
まずはその旨をお伝えしました。
そして、足底のアーチや脛腓関節、距腿関節などを意識的に整えました。
しかし、明確な原因を絞ることはできませんでした。
このように、白黒つけられない、グレーゾーン。
施術していると、よくあります。
早めにケアすることで、症状が慢性化することが避けられます。
また、カイロプラクティックでは症状のある部分だけでなく、体全体も施術します。
これは、体は部品で成り立っているのではなく、統合された有機体として捉えているからです。
治すのは患者さん自身が持つ自然治癒力。
カイロ・ウノではそのお手伝いをさせていただいております。
(-人-)~☆

「両足の踵(かかと)が痛いんです。」
とおっしゃいます。
ある日、夜に両足の踵が痛くて目がさめたそうです。
その日以降、夜になると決まって痛くなって、目がさめる…。
夜、睡眠を邪魔される
心配で、定期的に通っている整形外科でみてもらったが、
「異常はありませんね。」
といわれたそうです。
足底腱膜炎を考えたのですが、触診からも除外してもよさそうです。
夜間のみの痛みということでしたので、次回に経過を教えていただくことに。
先日、経過を伺うと
「痛み、消えました!」
と晴れやかな表情に。
そして
「原因、何だったんですかね?」
と聞かれました。
睡眠中に出てくることから、筋骨格系の刺激が低下することに起因するのだろうと推測できます。
まずはその旨をお伝えしました。
そして、足底のアーチや脛腓関節、距腿関節などを意識的に整えました。
しかし、明確な原因を絞ることはできませんでした。
このように、白黒つけられない、グレーゾーン。
施術していると、よくあります。
早めにケアすることで、症状が慢性化することが避けられます。
また、カイロプラクティックでは症状のある部分だけでなく、体全体も施術します。
これは、体は部品で成り立っているのではなく、統合された有機体として捉えているからです。
治すのは患者さん自身が持つ自然治癒力。
カイロ・ウノではそのお手伝いをさせていただいております。
(-人-)~☆