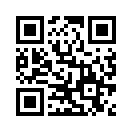2015年11月10日
アムチ小川の薬草講座(2.葛根湯について)
日本で唯一のチベット医であるアムチ小川(小川康さん)の講座に参加しました。
葛根湯といえば風邪の初期によく効くとされる薬。
意外でしたが、冷えからくる肩こり・神経痛・筋肉痛などの諸症状にも処方されることがあるそうです。
----------
葛根湯は7つの生薬で構成されています。
● 葛根 :筋肉を緩める
● 麻黄 :発汗を促進する
● 桂枝 :体を温める
● 芍薬 :筋肉痛をとる
● 生姜 :寒気をおさえる
● 大棗 :体を温める
● 甘草 :のどに効く(ムクミがでることがある)

葛根湯は中国では家伝薬の1つ。
その家に代々伝わる薬として、オリジナルの調合をおこなうのが当たり前。
「薬」というと敷居が高く感じますが、ハーブと同じように考えてよさそうです。
日本でも江戸時代から家伝薬があり販売されていたが、GMP基準によって規制されるように。
GMP基準は略語で、正式名称は以下の通りです。
● 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令
葛根湯は、飲む人の体調や症状によって、生薬の調合を変えるのが最適。
7つの生薬は、ほぼ購入できます。
「マイ葛根湯」、「葛根湯風」 というのも可能ですね。
あ!
もちろん売っちゃだめですよ! (^^;)
生薬は使用する前に、一度焙煎すると良いそうです。
焙烙(ほうろく)が1つあると便利かもしれませんね。
飲むときは、お茶と同様。
ポットに煎じた生薬を入れ、お湯を注ぎます。
一煎だけでなく、複数回大丈夫。
体に聴きながら、適量を飲むます。
度が過ぎると、体が受けつけなくなるそうです。
飲む時間は食前や食間など胃が空っぽな時が良いとされます。
これは、他の飲食物と一緒にとると効き目が悪くなってしまうため。
葛根湯の場合、体を温める作用が大事。
体全体になじませるよう、ゆっくりと飲みましょう。
-----------
強い毒性をもつ生薬は、薬としても効果が高いそう。
中国では麻黄、チベットでは附子(トリカブト)がこれにあたります。
その見極めができるのが、医者の腕。
チベット医には医学と薬学の境界(分業)がありません。
チベット医学の懐の深さを垣間見ることができました。
(-人-)~☆
----------
【参考ホームページ】
小川康(やすし)さん ホームページ
● 森のくすり塾 ホームページ
ネット記事連載
● 伝統医学のそよ風 〜ラダック・ティンモスガン村より〜
チベット医学について、詳しい情報が掲載されていました。
● ARURAチベット医学センター
薬の効能
● 成分名から探す(50音順) わかさ生活
葛根湯といえば風邪の初期によく効くとされる薬。
意外でしたが、冷えからくる肩こり・神経痛・筋肉痛などの諸症状にも処方されることがあるそうです。
----------
葛根湯は7つの生薬で構成されています。
● 葛根 :筋肉を緩める
● 麻黄 :発汗を促進する
● 桂枝 :体を温める
● 芍薬 :筋肉痛をとる
● 生姜 :寒気をおさえる
● 大棗 :体を温める
● 甘草 :のどに効く(ムクミがでることがある)
葛根湯は中国では家伝薬の1つ。
その家に代々伝わる薬として、オリジナルの調合をおこなうのが当たり前。
「薬」というと敷居が高く感じますが、ハーブと同じように考えてよさそうです。
日本でも江戸時代から家伝薬があり販売されていたが、GMP基準によって規制されるように。
GMP基準は略語で、正式名称は以下の通りです。
● 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令
葛根湯は、飲む人の体調や症状によって、生薬の調合を変えるのが最適。
7つの生薬は、ほぼ購入できます。
「マイ葛根湯」、「葛根湯風」 というのも可能ですね。
あ!
もちろん売っちゃだめですよ! (^^;)
生薬は使用する前に、一度焙煎すると良いそうです。
焙烙(ほうろく)が1つあると便利かもしれませんね。
飲むときは、お茶と同様。
ポットに煎じた生薬を入れ、お湯を注ぎます。
一煎だけでなく、複数回大丈夫。
体に聴きながら、適量を飲むます。
度が過ぎると、体が受けつけなくなるそうです。
飲む時間は食前や食間など胃が空っぽな時が良いとされます。
これは、他の飲食物と一緒にとると効き目が悪くなってしまうため。
葛根湯の場合、体を温める作用が大事。
体全体になじませるよう、ゆっくりと飲みましょう。
-----------
強い毒性をもつ生薬は、薬としても効果が高いそう。
中国では麻黄、チベットでは附子(トリカブト)がこれにあたります。
その見極めができるのが、医者の腕。
チベット医には医学と薬学の境界(分業)がありません。
チベット医学の懐の深さを垣間見ることができました。
(-人-)~☆
----------
【参考ホームページ】
小川康(やすし)さん ホームページ
● 森のくすり塾 ホームページ
ネット記事連載
● 伝統医学のそよ風 〜ラダック・ティンモスガン村より〜
チベット医学について、詳しい情報が掲載されていました。
● ARURAチベット医学センター
薬の効能
● 成分名から探す(50音順) わかさ生活